ビジネスの現場では、「収益率」とか「ROA」など、様々なビジネス数字にまつわる用語が出てきますよね?
今回の記事では、「その意味合いは何?」「経営上どんな意味がある?」ということをクイズというか、質問形式にして、皆さんに問うたいと思います。
このことで、あなた自身の知識レベルをさらに引き上げてもらえればと思います!それではいきましょう!
会社の資金調達において、株式発行と銀行借入れれの何を選択するかにより、下記の点にどのような影響を与えるでしょうか?
⑴ 自己資本比率
⑵ ROA(総資産利益率)とROE(自己資本利益率)
⑶ 会社のキャッシュ・フロー
⑷ 資本コストと企業価値
⑸ 支配権や株主構成
さぁ、いかがでしょうか?
用語だけは知っていても、「じゃあ、これって経営上どうなるの?」と聞かれると「???」となっている方もいらっしゃることでしょう。
これこそ、私どもが常に社員研修や経営者向け経営塾でお伝えしたい「原理原則を理解する」ということであります。
では、簡単にですが上記の内容を確認しますね。
⑴ 自己資本比率への影響
自己資本比率は、純資産と総資本(負債と純資産)の割合をみていく安全性の指標ですので、株式発行を利用すれば上昇し、銀行借入を利用すれば下降しますよね。
では、ここで「ふ〜ん」で終わらずに、もう1歩進んで考えてみてほしいのです。それは、下記のことです。
① 自己資本比率が高い、低いということの経営上の意味合いは?
② 自己資本比率を高めるためにはどうすればいいのか?
③ 自己資本比率が低いというのは経営上で必ず問題があるのか?
これらはあえて答えは示しません。ご自身で考えて自分なりの答えを見つけ出してほしいのです。なぜなら、そうしないとビジネスの現場で実践できる知識(見識/胆識)にならないからです。
⑵ ROA(総資産利益率)とROE(自己資本利益率)への影響
ROAとROAは「投資に対してどれだけリターンがあったのか?」という投資利益率の指標(収益性)です。
両者の違いは、分母にあり、前者が純資産+負債の総資本=総資産であるのに対して、後者は純資産のみです。
このため、ROAに関しては、株式発行と銀行借入のいずれを利用しても、構成割合に関係なく、分母は大きくなるという点では同じです。
これに対して、ROEは株式発行を利用すると純資産が増加するので、低下しますね。逆に借入を利用すれば、分母は変化なしなので低下しません。
では、ここで「ふ〜ん」で終わらずに、もう1歩進んで考えてみてほしいのです。それは、下記のことです。
① ROAとROEで両者の数値が大きく乖離するってことあるの?
② ROAとROEを高めるためにはどうすればいいのか?
③ 経営上はこれらの指標をどう扱えばいいのか?また、どちらの指標を注視すればいいのか?
これらはあえて答えは示しません。ご自身で考えて自分なりの答えを見つけ出してみてください。
なお、考える際のヒントとして、「デュポン公式の分解式」を調べてください。そこから「経営の視点」というもののヒントが得られます。
⑶ 会社のキャッシュ・フロー
株式発行は、出資を受けるということですので、資金運用の委託を受け、返済義務はありません。これに対して、銀行借入は返済と利息支払いの義務を負います。このため、CFに影響を及ぼしますね。
では、ここで「ふ〜ん」で終わらずに、もう1歩進んで考えてみてほしいのです。それは、下記のことです。
① 借入れを利用することによる安全性の問題(⑴ともリンク)をどう考えればいいのか?
② 安全性を気にして、借入れを利用しない(自己資本のみ経営)場合、ビジネスという点で、どんな問題が起こりそうか?
これらはあえて答えは示しません。ご自身で考えて自分なりの答えを見つけ出してみてください。
⑷ 資本コストと企業価値
株式発行と銀行借入のいずれを利用することで「資本コスト〜加重平均資本コスト」はどのような影響を受けるのか?ということです。また、そのことで「企業価値」にどのような影響を与えるのか?ということです。
これはファイナンス論の分野における「最適資本構成」の問題となります。
株式発行の場合は配当率が、銀行借入の場合は利率が資本コストとなりますが、一般的に配当の不確実性のある株式発行の方が資本コストは低いと考えられます(銀行借入の場合、利益に節税効果も働きます)。
しかし、借金ばかりだと銀行もリスクを感じるため、利率が上昇していきます。
そこで、両者のちょうどいい塩梅があるはずと考えるものが最適資本構成の問題となります。
企業価値に関しては、DCF法で考えた場合、分母の割引率に上記の加重平均資本コスト率を使うので、これが下がれば、企業価値は上昇すると考えられます。
では、ここで「ふ〜ん」で終わらずに、もう1歩進んで考えてみてほしいのです。それは、下記のことです。
① では、企業価値を高めるためにはどうすればいいのか?
② 企業価値計算で出てくるCFは利益とは違うのか?そもそも、収入・支出・儲けと収益・費用・利用は何が違うのか?
これらはあえて答えは示しません。ご自身で考えて自分なりの答えを見つけ出してみてください。
⑸ 支配権や株主構成
はい、これは分かるかと思います。株式発行と銀行借入の両者の違いとして、前者は会社の構成員になるため、経営に口出しされる。これに対して、後者は債権者ですので経営には口出しはされない、という点で異なります。
では、ここで「ふ〜ん」で終わらずに、もう1歩進んで考えてみてほしいのです。
それは、下記のことです。
① CFや安全性の影響を考えたら、株式発行を利用したいが、発行価額や発行数いかんによっては、会社の支配権に問題が出るが、それを回避する資本政策はどうすればいいのだろうか?
② 株式発行と銀行借入の両者のいいとこ取りができるような新しい資金調達手段というものはないのだろうか?
はい。今回は以上となります。
それで、このような内容のことを市販の教材やYouTubeの動画で身につけようと思っても、なかなか身につかないですよね?
そこで、当社は「ビジネスゲーム」を使い、これらのことを身につけていただく、社員研修や経営塾を開催しております。
「会社の未来を創るのは人です!」
企業の人材育成は会社の未来を左右する
課題の一つだと思います。
特に昨今の自動生成AIの登場は、
旧来の実務能力とは異なる能力を
社員さんたちに突きつけることに
なりました。
このため、旧来のありきたりな研修ではなく、
短時間でも効果が上がる新しい研修として
「ビジネスゲーム」を使った研修を
当社では提唱しております。
当社開発のビジネスゲームとは、ボードゲーム形式 により、ビジネス上で求められる「経営判断」や「チームビルディング」「経営数字の読み取り」といったスキルなどを直接的・間接的に疑似体験で学べるシミュレーションゲームです。
ゲーム形式で行うため座学による受動学習よりも、遥かに感覚的に身に付けることができ、 多くのメリットがあります。
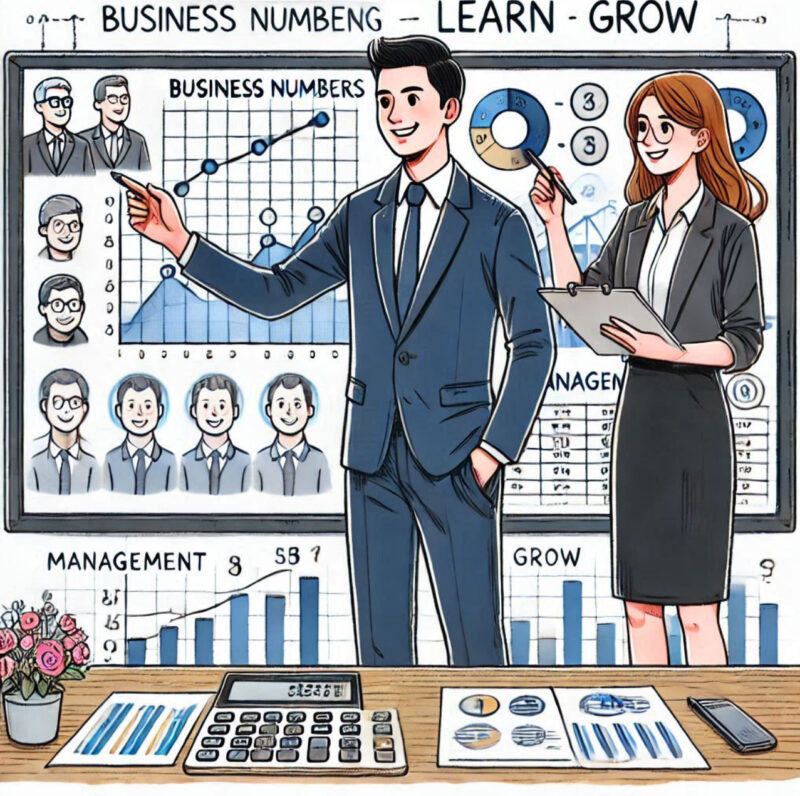
当社の研修では、ビジネスゲームを使い
下記のことをおこなって行きます。
①チームを組んでボードゲームで会社経営
②経営判断を行う
③自ら決算書の作成と分析を行う
④チームでワークとディスカッション
⑤事例分析を行う
このようなことをやっていただき、
ビジネスにおいて必要な「経営数字」を
メインに学んでいただきます。

当社のビジネスゲームを使うこと
による研修の効果は次のとおりです。
<ビジネスゲームを使った研修を受けることによる効果>
【効果1】
経営数字の観点からの「経営の視点」を身につける
【効果2】
ビジネスにおいて最低限必要な、経営数字
(会計・経営分析・ファイナンス)の知識を身につける
【効果3】
チームビルディングをとおして、役割分担、適材適所、
協働、相互牽制といった組織運営の基本を身につける
<上記の効果により得られるもの>
【効果1により】
「作業・業務」ではなく「経営の視点」で考えることができるようになる。
【効果2により】
定量情報による数字をツールとして活用できるよう になり、自社の状況を客観的に把握し、分析できるようになる。
【効果3により】
会社組織において必要な、人材の配置や役割分担、相互チェックやコミュニケーションの必要性を理解できる。
ビジネスゲームの種類
当社では、1回の研修時間を2時間から4時間程度に設定し、そのために
①ミニゲーム(短時間でできる)
②正規ゲーム(2時間〜3時間)
この2つをご用意しております。
また、会計などの経営数字の知識がない方、
初心者でも学べるゲームをご用意しております。

当社のビジネスゲームを使った研修では、
全国の様々な企業様、団体様で活用いただいて
おります。
・熊本日日新聞者様
・誠美社工業様
・税理士法人中央総合会計様
・第一実業株式会社様
・財務省九州財務局様
・熊本県商工会連合会様
・熊本学園大学様
・熊本市立総合ビジネス専門学校様
などなど

【研修の模様はこちら】
https://youtu.be/41-l2pnC-qU
【Facebookにて情報配信中】
https://www.facebook.com/mcassinc
【お問い合わせ先】
研修の詳細などの内容はこちらより
お問い合わせください。
https://m-cass.co.jp/contact.html